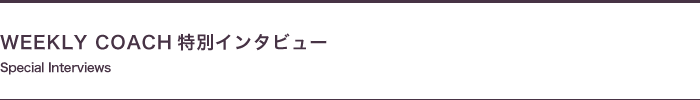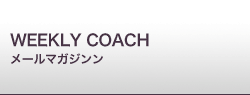「シュートは打ってみないと絶対に入らない」の気持ちで、 CTPを受講
-----では、プロコーチである喜熨斗さんが、CTPを受講したきっかけを教えてください。
日本には、サッカー協会が公認する指導者の免許制度があり、一般的にはDから始まって、C→B→Aという段階を経ていきます。その最高峰に位置するのがS 級ライセンスです。このライセンスは、日本代表やJリーグの監督をすることができる資格で、私も一昨年取得しました。年に20数名しか合格者が出ない狭き門です。
-----取得は相当大変だったのではないですか?
指導者である以上、学び続けることは当たり前だと思っていたので、大学での授業、専門スキルの講座、指導者としての実践、日々の読書と、サッカーやコーチに関するさまざまな学習を行ってきました。
CTPを学び始めたのは、A級ライセンス保持者として、次はS級にチャレンジしようというときでしたね。S級ライセンスというのは、さまざまな知識が重視されていて、その中には「モチベーションコントロール」「リーダーシップ」「コミュニケーション」といった分野も含まれていました。ところが、これらを専門的に学んだ経験が私にはなかった。そこで、知識を整理する意味でも、コーチングを学ぼうと思い、さまざまな養成機関を調べた結果、体系的に学習ができるCTPを受講することにしたのです。
-----受講にあたって不安要素などはありませんでしたか?

「自分のコミュニケーションやリーダーシップについて、さまざまな分野のプロフェッショナルからフィードバックを受け、分析していく」という受講の目的ははっきりしていましたが、多少のリスクも感じていました。一つは受講費用。そして、もう一つは投資に見合った成果が生まれるのか、という疑問。私が目指しているのは、あくまでも一流のサッカーコーチであり、CTPでコーチングを体系的に学んだからといって、必ず直結するという確証はありませんでした。
最後の決め手は、「シュートは打ってみないと分からない」という現役時代から持ってきた思いでしたね。
-----もう少し詳しく教えていただけますか?
「トライしないということは、ただ現状から逃げているだけかもしれない。変わろうとする勇気を失ってしまったら、この先だって何も変わらない。リスクを冒してでも、チャレンジしなくては」と。現役時代から、そうした気持ちを持ち続けていました。だったら迷っていないでCTPもやるだけやってみよう!と思ったわけです。
-----そうなんですね。では、実際受講してみて、どんな変化が生まれましたか?
承認や相手から引き出すスキル、質問の使い分けなど、それまで指導者として実践していたことも多々ありましたが、それらをもう一度体系的に学び直すことで、「効果的なアプローチの出し所」がより明確になったと思いますね。CTPは、クラスで受講したことを一週間実践で試してみて、それをまた整理していくというサイクルで学んでいくプログラムです。学習と実践の反復により、「あっ、このスキルはここで使うとより効果的なんだ」「この場面で、こういう質問は使えるな」といった具合に理解と行動がつながっていきました。
こうして、トレーニングを続けた甲斐もあって、一昨年S級ライセンスを無事取得することができました。この学びを活かして、今ではチームのフィジカルコーチとしてだけでなく、大学院の講師としてコーチ学も教えています。