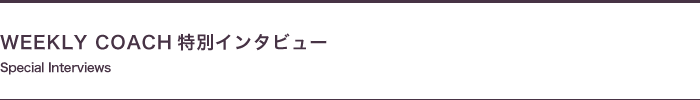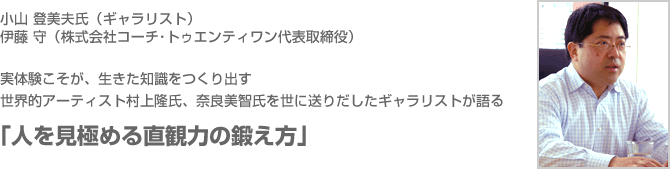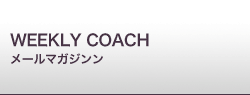村上隆氏や奈良美智氏を世に送り出したギャラリストとしてその名を広く知られる小山登美夫氏。そんな、数多くの世界的アーティストの作品を預かるギャラリスト・小山氏は、いったいどのように人を見極め、パートナーシップを構築してきたのでしょうか。今回は、特別企画として、小山氏と弊社代表取締役 伊藤守との対談が実現しました。

- 小山 登美夫氏
ギャラリスト
1987年東京芸術大学芸術学科卒業。1987年から1989年まで西村画廊勤務。1989年から1995年まで白石コンテンポラリーアートでの勤務を経て、1996年に江東区佐賀町に小山登美夫ギャラリーを開廊。奈良美智、村上隆を始めとする同世代の日本アーティストの展覧会を多数開催するとともに、同世代の国外アーティスト、トム・フリードマンやトム・サックスなどを日本に紹介する。またオープン当初より、海外のアートフェアへも積極的に参加。日本アーティストの実力を世界に知らしめるとともに、マーケットの充実と拡大を模索する。国内では1998年に“G9:New Direction”を東京の9件のギャラリーと一緒に企画。また2005年東京アートフェアのコミッティーを務めるなど、新しいギャラリーの方向性を提示する。

- 伊藤 守
株式会社コーチ・トゥエンティワン代表取締役
日本における最初の国際コーチ連盟マスター認定コーチ。 地方公共団体、教育機関、経営者団体などを対象とする講演多数。企業・経営者団体などを対象とした研修のほか、経営者の個人コーチも自ら手がける。またコミュニケーションに関する著書も数多く出版している。
アーティストを信じて、じっと待ち続ける
伊藤小山さん、こんにちは。今日はようこそお越しくださいました。
小山 こちらこそ、よろしくお願いします。それにしても、このオフィスから見える千鳥ヶ淵の桜はすごいですね。あそこには靖国神社があって、正面には日本武道館……。ここは本当に素晴らしい景色ですよ!
伊藤ありがとうございます。でも、今日は当初、小山さんのギャラリーにこちらからお邪魔しようと思っていたんですよ。僕の方は作品が見られなくて、ちょっと残念です(笑)
小山 それはすみませんでした。仕事の都合でこの近辺に来ていたもので、そのままこちらに伺ってしまいました。今僕のギャラリーは、東京都江東区と京都市下京区に一軒ずつ。また、エディション作品を扱っているギャラリーが、東京の銀座と京都に一軒ずつあります。エディション作品とは、同一絵柄の作品を限定数興しているもので、オリジナル作品に比べて購入しやすい価格で提供しています。今度、ぜひ立ち寄ってください。
伊藤 じゃあ、近いうちに必ずギャラリーに行かせていただきますね。
ところで、小山さんは、奈良(美智)さんや村上(隆)さんといった著名なアーティストの作品を多数扱っていらっしゃいますが、アーティストの方々とは、普段どのように接しているのですか?
小山 書籍『何もしないプロデュース術』(東洋経済刊)でも書きましたが、基本的にはアーティストが絵を描き上げるまで僕は何もしません。ただ、じっと待っている。

伊藤描いている作品にフィードバックとかしないんですか?
小山しないですね。例えば、テレビ番組のプロデューサーの方とかだと、番組が面白くなかったと判断した場合は、ディレクターに言って、内容を変えさせたりする のかもしれない。けれど、僕はそういうことはしません。アーティストが描きたいと思って描いたものを周囲がいじっちゃいけない、というのが僕の考え方なんです。
伊藤 そうなんですね。でも、そうしたら、アーティストの方が、自分の中にはない気づきを得る機会ってあるんですか?
小山 展覧会なんかで完成した自分の絵を客観的に見たとき、「あっ!」って気づくことが多いみたいですね。やっぱり、自分でも「これはだめだったな」と思うみたいで。そして、それを糧にまた創作活動に励む。そんなアーティストの作品を僕はじっと待ち続けているんです。
伊藤 なるほど。私もコーチという仕事をしていますが、相手が自分から行動するのを待ったり、ときには放っておいたりすることは結構ありますね。結局、最後にやるかやらないかを決めるのは本人次第なわけですからね。
小山 伊藤さんのおっしゃる通りです。僕の場合は、口を出さないからこそ、本当に自分にしっくりくるアーティストとだけ、仕事をするようにしています。そして、一度一緒に組んだら、どんなことがあってもそのアーティストを信じて待つ。それが僕なりの接し方ですね。
実体験こそが、生きた知識をつくり出す
伊藤 ところで小山さんは、なぜあれだけ著名なアーティストの方を次々発掘することができるんですか? この人はいける!」っていう直感をどのように鍛えているのか、そして、どこに目をつけているのかにとても興味があります。
小山 一つはより多くの美術の知識を身につけることですよね。美術には長い歴史や流れがありますし、過去のアーティストが描いてきた世界を熟知しておくことは不可欠です。そして、それを頭に入れておくことで初めて、これまでにあったものを違う形で描ける、新しいマーケットをつくり出せるアーティストを発掘していくことができます。
ただ、知識とはいっても、勉強や読書から得られる情報はほんの一部で、私の場合はほとんど実体験から得ています。自分の足を使っていろいろなところに出向き、これまでさまざまなアーティストの作品に触れてきました。海外や日本の展覧会はもちろん、京都や金沢といった地方都市へ学生の卒業制作も見に行きます。学校を卒業したばかりの若手アーティストの作品もどんどん頭に入れていくんです。最初は、「良い」「悪い」という判断はしないで、作品という「現象」にとにかくたくさん触れていく。そうしているうちに、徐々に自分の中で、「この人の作品は面白い!」という軸が生まれてきたんです
伊藤 その感覚、非常によく分かります。以前、ボストン・フィルハーモニーの指揮者であるベンジャミン・ザンダー氏とお話しする機会があったのですが、ザンダー氏によれば、クラシックの良し悪しの判断というのは、投資する時間に比例するんだそうです。時間をかけてたくさん聴いていると、そのうち何が良くて、何が良くないかがみえてくる、と。ワインとかもそうですよね。さまざまな種類の、さまざまな価値のワインを飲んでいくと、だんだんと味が分かってくる。あっ、これはあのとき飲んだワインよりも美味しいな」という具合に。
小山さんの場合は、良し悪しではなく、面白いかどうかが、判断基準ということですか?
小山 僕にとって、アーティストに対する唯一の肯定的な表現は、「面白い」なんです。よく、「小山さんは売れるアーティストの作品だけ扱っているんですか?」と聞かれるんですけど、そうじゃないんですよ。これまで世の中になかったような面白いアートを送り出していくことで、そこにマーケットが生まれ、歴史の種が撒かれ、展示会などが開催されるようになって、アーティストも成長していくんです。
美術のこれまでの価値観を、良い意味で壊し続けたい
伊藤 小山さんにとって、面白く、かつマーケットを生み出しやすいアートの条件のようなものはあるのですか?
小山 歴史化しやすいという点では、「破壊的な作品である」ということですね。例えば、前出の村上隆さん。彼の場合は、マンガという手法を使い、サブカルチャーとファインアート(純粋芸術)を同列視しました。これは、アメリカでは掟破りであり、だからこそ、「破壊的」なわけです。
奈良美智さんの絵にしてもそうです。「子どもの孤独な顔」というあんな感情的な絵を美術に持ち込むアーティストは、現代美術の歴史的に見てこれまでほとんどいなかった。セザンヌなどのファインアートはもちろん、ピカソも「ゲルニカ」こそ例外ですけど、ほとんどなかったですよね。最近は、どちらかというと宗教画に近いかな。けど、僕はそれを面白いと思った。そして、そこにマーケットができて、徐々に今のような評価につながっていったんです。

伊藤 私は奈良さんの作品を見たとき、なんだか昔に戻ったような、懐かしい気分になりましたよ。
小山 人間って、世界のどこにいても、必ずどこかでつながっていると思うんです。奈良さんの作品の感情的な部分は、21世紀を生きる人々の「疎外感」のようなものを表しています。アメリカでもヨーロッパでも、アジアでも、「人は本来一人きり」という感覚は共通しているからこそ、受け入れられるんだと思いますね。
伊藤 なるほど。それで、私も懐かしい気持ちになったのかもしれませんね。つまり、小山さんは、破壊的な現代アートを手がけることで、美術のこれまでの価値観を良い意味で壊しているといえるわけですね。
小山 僕の中には、美術の世界のためだけの美術ではなく、もっと美術を、社会的な問題とか、人間の活動を反映するような豊かなものにしていけたらいいな、という気持ちがあり、常にそれを意識して活動したいと思っています。
そもそもアートの値段はどのように決まるのか
伊藤 今や億の値段で取り引きされることも珍しくない村上さんや奈良さんの作品ですが、そもそもアートの値段というのはどのように決めていくんですか?
小山 アートのマーケットには2つの値段が存在しています。一つはプライマリー・プライス。これは、作品が初めて世に出るときの価格で、ギャラリーで売買をする場合、その値段はギャラリストが決めています。もう一つは、セカンダリー・プライスといって、2回目以降の売買の際に付けられる価格です。オークションでの価格などはこちらにあたります。僕が付けているのは、プライマリー・プライスの方ですね。
伊藤 最初から強気でいくんですか? それとも少しずつ上げていくとか?

小山 今までの作品で付けていた値段や価値から判断して決めます。前の作品がこのくらいだったから次はこのくらい、みたいな。ただ、同じ作品でも、二次売買におけるオークションなどでグワッと値段が上がることもありますから、そのときは前の作品のセカンダリー・プライスを意識して付けることになります。プライマリー・プライスとセカンダリー・プライスにあまりに差がありすぎると、その差益で儲けようとする人が出てきてしまいますからね。
伊藤 なるほど。いろいろな要素がからんでいるわけですね。ちなみに、村上さんの最初の作品って、いくらくらいだったんですか?
小山 確か2万円くらいだったような…。
伊藤 2万円! そんな安かったんですか!? そのとき買っていた人は、相当先見の明があったということですね。ちなみに、ずっとそのくらいの値段のまま終わってしまうアーティストもいるんですか?
小山 実際にはいますね。でも、まあ、うちのギャラリーではだいたい、2万円くらいから始まって、価値が認められるにしたがって、10万円、20万円、50万円、100万円と徐々にプライマリー・プライスを上げていきます。価値が認められるには、より多くの方に名前や作品を知っていただき、売れる種を撒いていかなければなりませんけどね。そこは、ギャラリーの方でPRをしたり、情報発信をしたりしてサポートをするわけです。
伊藤 値段が下がることはないんですか?
小山 下がることもありますよ
伊藤 値段が下がったら、アーティストのモチベーションも一緒に下がってしまいそうですが、どうなんでしょうか?
小山 僕の見ている限りでは、アーティストはそんなに気にしてはいませんね。セカンダリー・プライス次第で、ガーっと上がることもあれば、ダーンと下がってしまうこともあって、パターンはさまざまですから、いちいち一喜一憂しないというか。
それに、たとえ値段がいくらであっても、アーティストの中では、前の作品と次の作品はつながっていくものなんです。ですから、金銭的な意識よりもむしろ、「今回の作品はこうだったけど、次はどうしよう?」 「今度はちょっと実験してみようかな?」という具合に、自分の創作活動の方に没頭するアーティストのほうが多いと思いますよ。
自分で考え、自分の価値観で決断を下す喜び
伊藤 ということは、あまりビジネスライクには仕事をしていないということですか?
小山 ええ。僕も含め、アートの世界ではお金以外の部分で決断を下すケースが往々にしてあるんです。先ほど、自分にしっくりくるアーティスト以外とは仕事をしないようにしていると言いましたが、以前も大変著名なアーティストから依頼を受けたにもかかわらず、丁重にお断りしたことがあります。もちろん、ビジネスで考えたら、絶対にやった方がいいとは思いましたけど、「儲かれば何でもいい」ってわけじゃないですからね。
しかも、自分が「面白い」と思っていない方と仕事をして、もしうまくいかなかったら目も当てられない。人に言われたり、話を持ちかけられたりしてやるのも好きじゃありません。たとえ成功したとしても自分自身が面白くないですから。
伊藤 それは同感です。よく「うまい話」とかいうじゃないですか。でも「うまい」というくらいだから、そんな話、絶対にありえないですよね。儲かるなら、自分でやればいいのにと思ってしまう。私はこれまで、いくつも会社をつくってきましたけど、すべて自分の意思で、自分がやりたいと思って始めてきたので、小山さんのおっしゃっていることはよく分かりますよ。

小山 やっぱり、僕はこれからも自分が「面白い」と思えるアーティストとパートナーを組み、新しいマーケットをつくり、歴史的にも「面白いな~」とみなさんに振り返ってもらえるような活動を続けていきたいですね。
僕、本当に面白い作品を前にしたときは、「こんなことまでやっちゃっていいの!?」 「そんなことやって、本当にバカだね~」ってつい言っちゃうんですけど、この、僕にとっての最高のほめ言葉を、これからももっともっと言えるように、数多くの作品やアーティストに出会っていきたいと思っています。
伊藤 これからもますます「面白い」作品を世に送り出してくださいね。今日は本当にありがとうございました。この話の続きは、また今度小山さんのギャラリーで…。
小山 ぜひいらしてください。お待ちしています。こちらこそ、今日はありがとうございました。
【インタビュー実施日:2010年4月13日】
構成:コーチ・トゥエンティワン 花木 裕介
カメラ:コーチ・トゥエンティワン 戸田 ちえ子
いかがでしたか? この記事に対するあなたのご感想や小山登美夫氏への質問などを、以下までお寄せください。 メールの宛先:editor@coach.co.jp
小山登美夫ギャラリー・TKGエディションズのご案内
小山登美夫ギャラリーは現在以下4店舗です。TKGエディションズでは、エディション作品を扱っています(エディション作品とは、同一絵柄の作品を限定数興しているもので、オリジナル作品に比べ購入しやすい価格で提供しています)。興味をお持ちの方は、ぜひお近くのギャラリーへお立ち寄りください。
- 小山登美夫ギャラリー
- 〒135-0024
東京都江東区清澄1-3-2-7F (丸八倉庫ビル) - 小山登美夫ギャラリー 京都
- 〒600-8325
京都府京都市下京区西側町483番地(西洞院通 / 新花屋町通 西南角)2F - TKGエディションズ
- 〒104-0061
東京都中央区銀座1-22-13 銀座カーサ1F - TKGエディションズ 京都
- 〒600-8325
京都府京都市下京区西側町483番地(西洞院通 / 新花屋町通 西南角)1F
- 詳細は TOMIO KOYAMA GALLERY.com へ