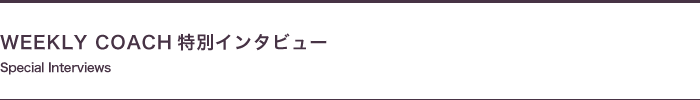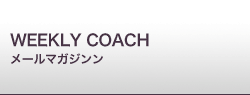常に勝つことを義務づけられているラグビー界の名門、早稲田大学ラグビー蹴球部。勝ち続けるチームに育て上げるため、コーチ陣は日々どのような取り組みを行っているのでしょうか。
今号より、コーチ・トゥエンティワンのサポートの元、早稲田大学ラグビー蹴球部のフルタイムコーチを務める有水剛志氏に、スポーツコーチとしての選手育成のポイントや、ビジネスコーチとの共通点などを3回にわたって、語っていただきます。

- 有水 剛志氏
早稲田大学ラグビー蹴球部コーチ
鹿児島県出身。1997年早稲田大学卒業。在学中は、ラグビー蹴球部に所属。現監督の中竹竜二氏とはラグビー部にて同期。卒業後、日本国土開発に入社。 2000年、ラグビークラブチーム、タマリバクラブの設立に携わる。2006年中竹監督就任時より、母校ラグビー蹴球部のフォワードコーチを務める。 2009年10月、株式会社コーチ・トゥエンティワンのサポートのもと、ラグビー部のフルタイムコーチに就任。現在、コーチ・トゥエンティワン提供のリー ダーシップ開発のプログラムを受講中。
第1回 観察と個別対応が選手の強みを最大限に引き出す
-----現在、早稲田大学ラグビー蹴球部には、何名のコーチがいらっしゃるんですか?
私を含めて15名です。フルタイムだけではなく、土日祝日だけのパートタイムのコーチもいます。この人数で、総勢132名の部員の指導をしています。
-----15名もいたら指導方法も異なるのでは?
もちろんそうですね。ある選手に対して、「こうしてみれば?」というコーチもいれば、「あのやり方を続けた方がいい」というコーチもいます。でも、それで いいんです。いろいろな選択肢がある中から選手は自分で考えて選んでいくのですから。
-----なぜそのような指導が可能なんですか?
最終的な目標や方向性が、メンバー・スタッフ全員にきちんと統一されているからでしょうね。早稲田の場合は、まず何といっても「絶対勝つ」こと。そのため に、選手の力を最大限に引き出す。それがぶれなければ、そこに至るプロセスはいろいろな形があっていいじゃないか、ということがコーチ陣とメンバーの中で 共有されています。

-----有水さんはどんなスタイルで指導しているんですか?
私の場合は、「気づき」を与える指導法ですね。基本的には、ティーチングの場面が多いんですが、あまり深く教えすぎないようにしよう、なるべく本人に気づ かせよう、と心がけています。頭ごなしに言ってしまうと、相手はそれを丸覚えするだけで、応用が効かない選手になってしまうからです。
-----例えば、どんなケースですか?
試合中、うちのメンバーがボールを持って走っているとき、相手選手にタックルされるようなシーンがあります。そのとき、次にボールをどうやって活か すかがラグビーではとても重要なんです。そして、ボールの活かし方は、タックルを受けた後の倒れ方によって、まったく異なってきます。
そんなときもし、「こういう場合は、こう倒れるんだ」と一方的に指導して理解させたらどうなるでしょうか。確かにまったく同じようなタックルを受け たときは教えたことを実践するでしょうが、少し角度が違っていたりすれば、また一から指導が必要になるでしょう。

-----それでは、自律的な選手には育たないですね。
その通りです。ですから私は、別のシチュエーションであっても自分で考えて解決しようとする選手を育てるため、そのシーンにおける「肝や本質だけを教え る」ことに注力しています。「ボールを活かすためにはこれだけは絶対に意識しなければいけないよ」という具合に。それだけきっちり指導すれば、選手は自ら 気づき、次は自分で考えて最善のプレーをするようになります。
-----他に有水さんが意識されていることはありますか?
あとは、とにかく観察ですね。相手の性格やタイプ、特徴などによって対応を変えていかなければ、各選手の能力を最大限に引き出すことはできません。コーチ ングでいう「個別対応」ですね。
-----具体的には?
もともと観察するのが好きというのもありますが、常に「どうすれば彼のモチベーションを高められるだろう」といったことを考えながら、選手を見ています。 そして、選手の個性に合わせて、たとえ同じミスをしたとしても相手によって教え方を変えていますね。叱られることで、「なにくそ」と思って伸びるタイプも いれば、「今のはこうした方がいい」と具体的にアドバイスをした方が伸びるタイプもいます。こうした感覚を磨くには、いつでも目的意識を持って選手を観察 することです。
-----観察のポイントはどんなところにありますか?
普段の何気ない場面よりもむしろ、「きついメニューをやらせているとき」「楽なメニューをやらせているとき」「緊迫した場面」といった状況にこそ、人の本 質は出てくるものです。なので、あえてそういう練習を課して観察することもあります。経験上、きつい状況を自ら乗り越える力を持っている選手には、少し厳 しく言った方が伸びる傾向がありますね。

-----ということは、日ごろからずっと選手を見ていなければなりませんね。
もちろん、それが理想です。私も以前は仕事の都合上、パートタイムコーチとして、土日祝日だけ指導をしていました。しかし、普段の彼らを知らないのに、試 合のときだけ「そうじゃないよ」と指導をした場合、どうしても評論家的になりがちです。やはり、日ごろから気にかけ、観察し、そのプロセスを知った上で指 導することで、個別対応はより機能するんだ、と実感しています。