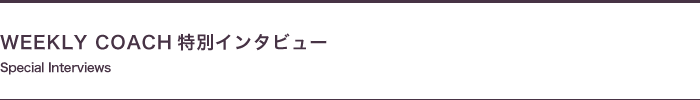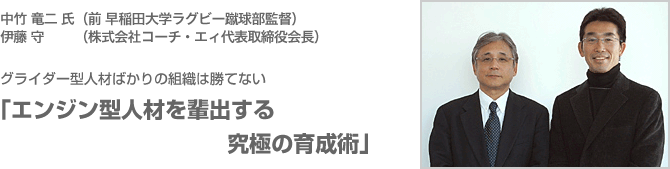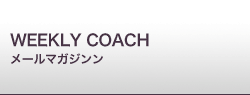前回の記事 コーチの役割は、『うまく教える』ことではなく『チームを勝たせる』こと
過去2年間、大学選手権2連覇を成し遂げ、昨年の関東大学ラグビー対抗戦も逆転で優勝を飾った大学ラグビー界の名門、早稲田大学ラグビー蹴球部。その早稲田大学ラグビー蹴球部の監督を務める中竹竜二氏をお招きし、Coach's VIEWでもおなじみの伊藤守(コーチ・エィ代表取締役)とさまざまなテーマで語り合っていただく特別対談最終回をお送りします。最終回のテーマは、変化への適応や変化を生み出すことの重要性。組織のトップに立つ二人はどのように「変化」を生み出しているのでしょうか。
最終回 変化は人を成長させる、そして、組織を強くする
勝つためにあえて環境の変化を起こす
伊藤 「130名を超える部員を束ねるのは大変だと思いますが、メンバーは毎試合、中竹さんが決めているんですか?」
中竹 「そうですね。ラグビーはいつけが人が出てもおかしくないスポーツですし、今の早稲田は1軍から6軍全員で勝つラグビーですから、誰にだって出場するチャンスがあります。昨年の早明戦でもスタメンが4~5名くらい戦列を離れる事態が起こりましたが、けが人が出たらどんなに実力差があったとしても、誰かが代わりに出なければならない。ですから、リスク管理の意味でも、選手には同じ気持ちで、妥協することなく、常に勝利を目指してもらわないといけません」
 伊藤
「けが以外でも選手を入れ替えることってあるんですか?」
伊藤
「けが以外でも選手を入れ替えることってあるんですか?」
中竹 「ありますよ。例えば、1年の頃から試合に出続けて、2連覇を達成したときの主力メンバーがいるんですけど、ある日を境にメンバーから外したことがあります」
伊藤 「そうなんですか? その選手は面白くなかったでしょうね」
中竹 「当然、ふてくされますよね。『何で俺が…』という気持ちだったでしょう。でも彼はそこから変わりました。コーチ陣が指導したわけでもないのに、自分のエンジンを使ってすごく伸びたんです。ところが、同じ時期にメンバー落ちしたもう一人の子は、コーチにべったりで、あまり成長が見られませんでした。つまり、成長のためには時に突き放すことも必要だということです。変化に対してどう適応していくか、どう自分を変えていくかは、選手が成長する上で重要なポイントですからね」
伊藤 「すごく伸びた選手は、環境に左右されることなく、自分でエンジンを動かして飛び立った。一方、伸びなかった選手は環境や周囲に身を任せていた、ということですね」
中竹 「そうですね。あと、別の事例で、成長株の二軍の選手が『そろそろ俺も一軍かも…』なんて考えているのが分かったとき、逆に三軍に落としたこともありますよ。そういう選手は、口には出さないもののすでにプレーに甘さが出てしまっているんです」
伊藤 「その選手が、そこからもう一度這い上がってこなかったらそれまでの選手、ということですよね。他に勝利のためにとった起用方針はどんなものがありますか?」
中竹「これはある時期の二軍の公式戦でのことなんですが、決勝の大舞台で、それまでキャプテンを務めていた選手を先発メンバーから外したことがあります」
 伊藤
「キャプテンを? それはまた大胆ですね」
伊藤
「キャプテンを? それはまた大胆ですね」
中竹 「ええ。ずっと出場して、チームを引っ張ってきた選手をあえて外しました。当然、彼は納得しませんよね。『なぜ俺を外すんだ』って。でも私は勝つためにその戦術とメンバーを選び、そして彼にこう言いました。『いいか。俺はお前に後半20分から出場して、とてつもないビッグプレーをしてほしい。一番緊張感の高い場面で出すからな』と」
伊藤「結果、その選手はどうだったんですか?」
中竹 「後半20分から出てきて、勝利につながるプレーをしてくれましたよ。勝つために起こした環境の変化を、自らの力で乗り越えてくれましたね」
変化にワクワク感を感じるくらい、タフなチームへ
伊藤 「ところで、中竹さんのそういう起用方法はどんな信念に基づくものなんですか?」
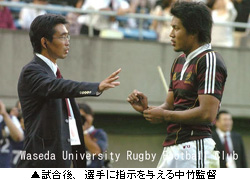 中竹
「私の場合は、『勝つ』ためにどうするかがすべてです。そのために各コーチからもいろいろと意見を聞きます。でも、『最後に決めるのは私だから、言われたとおりになっていなくても文句を言わないでくれ』と伝えています。まあ、後になってワーワー言われちゃうこともありますけどね(笑)。その判断基準は、あえて言えば、これまでやってきた勘でしょうか。明確な理由って、実はそんなにないんですよ」
中竹
「私の場合は、『勝つ』ためにどうするかがすべてです。そのために各コーチからもいろいろと意見を聞きます。でも、『最後に決めるのは私だから、言われたとおりになっていなくても文句を言わないでくれ』と伝えています。まあ、後になってワーワー言われちゃうこともありますけどね(笑)。その判断基準は、あえて言えば、これまでやってきた勘でしょうか。明確な理由って、実はそんなにないんですよ」
伊藤 「分かります。理由なんてないし、いちいち求めてくるような人間は、いつまで経ってもエンジン型にはなれません。人は変化に対して、とかく理由を求めがちですけど、これってただ安心感を得たいだけなんですよね。『理由は分からないけど、その環境に対して、いても経ってもいられなくなって、思わずエンジンかけちゃった』。そんな選手が伸びるんじゃないですかね。『とにかくやってみよう』というような」
中竹 「確かに。今の若い人は説明がないと、動かなくなってきていますよね。でも、すべて説明するんじゃなくて、『いいからやってみろ。理屈は後で分かるから』という指導を取り入れているコーチもいます。そういうコーチに付いていくことで、選手は徐々に変化を受け入れ、適応できるようになっていく。
実際、今の選手たちはかなりタフになりましたよ。私が監督になってからというもの、チームは毎年、戦い方を変えているんですが、今年は11月に入るまで具体的な戦い方を明示しませんでした。今年はなぜか予感めいたものがあって、メンバーも固定しませんでした。結局、インフルエンザやけがの影響で、先日の試合も5~6名のレギュラーが欠けた状態だったんです。でも、そんな環境も選手をタフにしていきましたね。レギュラーが抜けても、慌てることなく、『次は誰がレギュラーなんだろうな』『中竹さんのことだから、全然違うところから引っ張ってくるかもな』なんて。よくここまでタフになったなと思いますね」
伊藤 「いいですね。普通はだいたい決まったメンバーで試合して、何かあったときだけ入れ替える、というのが主流ですよね」
中竹 「その通りです」
伊藤 「でも、大リーグなんかに象徴されるように、その流れは確実に変わってきましたよね。コーチングはチェンジマネジメント、つまり変化に対してコーチングをしているわけです。でも、今はもう変化に適応させるだけでは、時代の流れとして間に合わない。チェンジをこちらからどんどん起こしていくほうがいいんです。
そして、変化が起きていることに幸せやワクワク感を感じるくらいの組織が、本当に強い組織になっていくんだと思いますね。『おっ、また変わるぞ!』というようなね。そうしたところに早稲田大学ラグビー蹴球部の強さがあるんじゃないでしょうか。変化に対するフレキシビリティーの高さゆえ、たとえ負けていても、彼らは最後の最後になんとかしてしまうんじゃないかな、と私は試合を見ていていつも感じるんですよ」
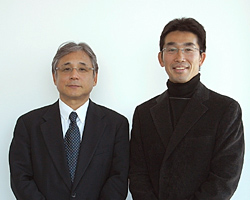 中竹
「そうおっしゃっていただけると励みになります。今の選手たちはあらゆる変化に慣れていますから、まだまだ底が見えない。私自身にも分からないくらいです。これからも勝利だけを目指していろいろと取り組んでいきたいですね」
中竹
「そうおっしゃっていただけると励みになります。今の選手たちはあらゆる変化に慣れていますから、まだまだ底が見えない。私自身にも分からないくらいです。これからも勝利だけを目指していろいろと取り組んでいきたいですね」
伊藤 「これからも変化を生み出し続ける中竹流リーダーシップに期待しています。今日は本当にありがとうございました」
中竹 「こちらこそ、今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました」
インタビュー実施日:2009年12月17日