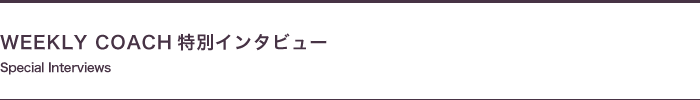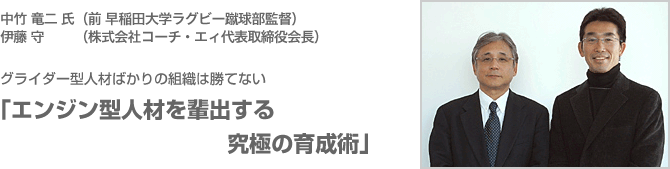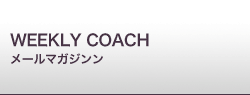前回の記事 第1回 一流を見極め、三流を活かす
過去2年間、大学選手権2連覇を成し遂げ、昨年の関東大学ラグビー対抗戦も逆転で優勝を飾った大学ラグビー界の名門、早稲田大学ラグビー蹴球部。その早稲 田大学ラグビー蹴球部を率いる中竹竜二氏をお招きし、Coach's VIEWでもおなじみの伊藤守(コーチ・エィ代表取締役)とさまざまなテーマで語り合っていただく特別対談第2回をお送りします。今回のテー マは、二人の持つコーチング論やリーダーシップ論です。
第2回 コーチの役割は、『うまく教える』ことではなく『チームを勝たせる』こと
周囲を巻き込み、自ら変革を生み出すのが真のリーダー
中竹 「伊藤さんは、『リーダーシップとは、そこにいる人たちを参加させる能力』とおっしゃっていますが、実際のビジネスシーンでは、部下育成においてどのようなリーダーシップが求められているのですか?」
伊藤 「私たちが育成しているのは、周囲を巻き込み、勇気を持って自ら変革を生み出すリーダーです。ところが、会社組織では、『もし失敗したら、私の人生どうなっちゃうんだろう?』と、部下の指導に怯える上司も少なからずいます。今はメンタルの問題など、かつてないほどデリケートになってきていますからね。しかし、そういった恐怖に立ち向かっていかないとリーダーシップは発揮できないと私は思います。中竹さんはそんな恐怖心を感じることはありませんか?」

中竹 「うーん、ないですね。私にしてみたら、負ける恐怖に比べたら、そんな恐怖どうってことありません。とにかく勝つこと、一番になること。それだけを目指してやっていますから。選手に怯えていては指導になりません。他にはどのような上司がいるのですか?」
伊藤 「そもそも部下やメンバーを育てようと思っていない上司ですね。経営者が20~30代の若手をもっと使おうと思っても、50代が蓋をしていて動けない、なんていう職場が結構見受けられます。ベビーブーマー前後の世代が、既得権を侵されないようにしているんですよ。でも組織の将来を考えたら、それでいいはずがない。本当に部下のことを考えているのなら、酒に誘って云々語るのではなく、部下を実践に巻き込むのが一番ですよ。『この仕事一緒にやろう』と。そこで、部下の力を見極めていくんです」
中竹 「一流でない部下はどうなるんですか?」
伊藤 「部下のほうでも、本当に勝ちたいと思っているのなら、一流も二流も関係ありません。今の環境を嘆くのではなく、下克上を起こすくらいの勇気やタフさが必要じゃないでしょうかね。そこから真のリーダーシップが生まれてくるんだと思います」
二番ではなく、あくまでも一番を目指す
伊藤 「ところで、中竹さんは、選手の人事だけでなく、(会社でいうと上司にあたる)コーチ陣の人事も一手に引き受けているんですよね。コーチたちに対しては、どのような評価基準を設けているんですか?」
中竹 「時間を決めてそれぞれと面談するんですが、『こういうコーチングスキルを使っています』とか『こういう指導をしています』というのはあまり評価しません。逆に、『選手のこういうところが伸びました』といった成果で語れるのが優秀なコーチだと思います。正直、コーチング力なんて0点でもいいんです。選手が伸びて、結果を出しているのなら」
 伊藤
「ビジネスシーンでコーチングを活用している方の中にも、身につけたスキルを使うのが目的になってしまっている人がいますよ」
伊藤
「ビジネスシーンでコーチングを活用している方の中にも、身につけたスキルを使うのが目的になってしまっている人がいますよ」
中竹 「ええ、ええ。『勝つ』ためではなく、『教える』ためにコーチをしている人ですよね。海外とかでスポーツのコーチングを学んできているような人によく見られる傾向で、とにかく教えたくて仕方がないんです」
伊藤 「『勝つ』という目的で集まっているのに、その意識を持っていない人がいると、チームは徐々に崩れていってしまいますよね」
中竹 「はい。それから、よく聞くのが『僕たちの頃は』と言うせりふ。過去の成功体験で語ろうとするんですね。そんなときは、『基準はそこじゃないないから』とはっきり言います。過去も去年も基準にはならない、と。今年どうやって勝つかが重要なんだ、と」
伊藤 「中竹さんの『今勝つこと』に対する意識には非常に惹かれますね。話は変わりますが、先日ある勉強会に参加したんです。そこでiPS細胞の研究で知られる山中伸弥先生(京都大学再生医科学研究所)からお話を伺いました。特に印象的だったのは、山中先生がiPS細胞の論文を提出した約8時間後には、アメリカでも同じような論文が提出されたという話。要は、僅差なんですよ。すべてのことは僅差で起こっているんです。そして、彼は研究所を作るわけですが、それも『世界レベルじゃだめ』だそうです。『世界一じゃなきゃだめ』なんですって。そうしたくっきりしたエッジがないと、あっという間に『普通』に成り下がってしまうんでしょうね。早稲田の場合もそうではないですか? 一番になって、あわよくば実業団とか世界を食ってやろうなんていう気持ちがあるのでは?」
 中竹
「そうですね。実は今年に関しては、チーム作りの中でとことん取り組んだことが一つあります。それはタックルです。『とにかく世界一タックルにこだわるチームにしよう』と。例えば夏合宿。このときは、練習時間の7割くらいはタックルやってましたね。正直、ここまで極端に時間を割いているチームないですよ。でも、この時期だけは、タックルだけならオーストラリアにもニュージーランドにも負けない。そんな練習をして自信を深めてきたことを思い出しますね」
中竹
「そうですね。実は今年に関しては、チーム作りの中でとことん取り組んだことが一つあります。それはタックルです。『とにかく世界一タックルにこだわるチームにしよう』と。例えば夏合宿。このときは、練習時間の7割くらいはタックルやってましたね。正直、ここまで極端に時間を割いているチームないですよ。でも、この時期だけは、タックルだけならオーストラリアにもニュージーランドにも負けない。そんな練習をして自信を深めてきたことを思い出しますね」
伊藤 「かつてジャイアンツに在籍した王さん、いたじゃないですか、ホームラン数世界一の。でも、あの王さんだって最初の3年間は泣かず飛ばずだった。そこでついたあだ名が『なまけもの』。ところが、ヒットやホームランが出始めた途端、俄然努力をし始めた。こうした体験をさせて本人のやる気に火をつけるのも、コーチの役割でしょうね。『世界一のタックル』も同じだと思いますよ。選手はその気になっちゃうでしょうから。『世界一』とか『勝つ』とかっていうのは、人の脳に及ぼす好影響があるんだと私は思いますね」